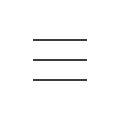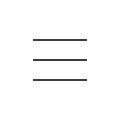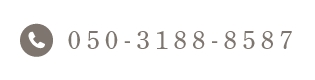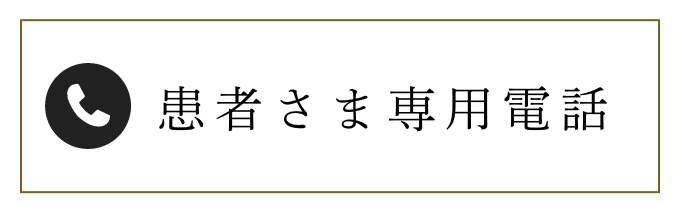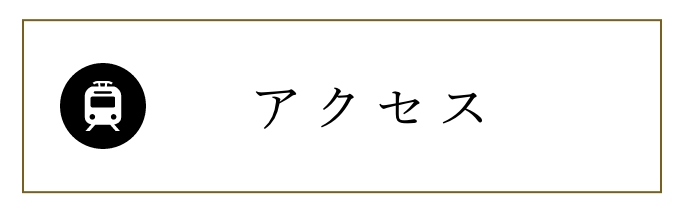ブログblog
歯周病専門医によるメンテナンスの必要性|代官山エリアでの通院ポイント

こんにちは。代官山WADA歯科・矯正歯科の歯科医師です。
歯周病の治療には「治療期」と「維持期(メンテナンス)」があります。治療期で炎症が落ち着き、歯ぐきの腫れや出血が改善しても、それで終わりではありません。むしろ、そこから先のメンテナンスの質が、数年後の歯の残存数やインプラント・被せ物の安定、そして生活の質に直結します。
今回は、歯周病専門医の立場から、メンテナンスがなぜ必要なのか、何をどの順番で行うのか、そして代官山エリアで無理なく通うための現実的なポイントまで、丁寧にお話しします。
目次
- メンテナンスは「治療の延長」ではなく「再発を防ぐ主治療」
- 専門医のメンテナンスが違いを生む場面
- 来院ごとに何をしているのか:診査・記録・バイオフィルムコントロール
- リコール間隔は“人それぞれ”で決まる:リスクに合わせる考え方
- ホームケアが続かない理由と、現実的に続く方法
- 代官山エリアで通院を続けるための工夫(アクセス・時間設計・組み合わせ受診)
- インプラント・矯正・補綴と「維持期」の接続
- まとめ:小さな変化を見逃さないことが、将来の歯を守る
メンテナンスは「治療の延長」ではなく「再発を防ぐ主治療」
歯周病は、細菌による慢性炎症が歯ぐきや骨を少しずつ壊していく病気です。スケーリングやルートプレーニング、必要に応じた外科処置によって炎症を抑え込むことはできますが、口腔内に歯周病原性の細菌がゼロになるわけではありません。時間が経てばバイオフィルム(細菌の膜)は再形成され、自己流の清掃では届かないポケット内に定着します。
この“再形成のサイクル”を定期的に断ち切るのがメンテナンスの役割です。私は、メンテナンスは「治療の後片付け」ではなく、再発を防ぐ主治療だと考えています。治療で得た健康な歯周組織を守るフェーズこそ、患者さんの将来を左右するコアになります。
専門医のメンテナンスが違いを生む場面
炎症の兆候は、必ずしも痛みとして現れません。ポケットのわずかな深さの変化、出血点の増加、排膿の痕跡、動揺度の微細な変化、咬合の当たり方のズレ。こうしたサインは、記録と比較、触診の感覚、プローブ圧の再現性があって初めて“変化”として見えてきます。
また、補綴物(被せ物)のマージン形態やインプラント周囲の軟組織ボリュームは、清掃性に直結します。専門医の視点では、単に「汚れを取る」だけでなく、炎症の原因が構造にないかを見立てるところまで踏み込みます。必要に応じて補綴の微調整や装置の形態見直しを提案し、そもそも汚れが溜まりにくい環境へ近づけることが、長期安定の分岐点になります。
来院ごとに何をしているのか:診査・記録・バイオフィルムコントロール
メンテナンスでは、最初に口腔全体の診査から入ります。歯周ポケットの深さ、出血や腫脹の有無、動揺度、プラーク付着の分布、噛み合わせの接触関係、口呼吸・舌癖の傾向などを、前回の記録と整合させながら確認します。
次に、バイオフィルムの破壊と再付着抑制を目的に、機械的清掃を行います。歯肉縁上は見た目より“触覚”が重要ですし、縁下はチップや手用器具を部位ごとに変えながら、必要最小限の力で滑沢に整えます。仕上げに染出しや写真で“見える化”し、患者さん自身が「どこに・なぜ・どうやって」汚れが残るのかを理解できるようにします。
最後に、ホームケアの確認とアップデートです。同じアドバイスの繰り返しではなく、生活の変化(在宅勤務、育児、出張、矯正中など)に合わせて道具の選択と手順を入れ替え、“今日から現実的にできる”宿題に落とし込みます。
リコール間隔は“人それぞれ”で決まる:リスクに合わせる考え方
「三か月ごとで良いですか?」というご質問をよくいただきます。目安としては妥当ですが、最適解は人により異なります。喫煙、糖尿病、ストレスや睡眠の質、歯並びや補綴の清掃性、インプラントの有無、出血点の推移、ポケットの残存深さ。これらが総合的に“再発リスク”を形作ります。
初期は一〜二か月間隔で炎症をゼロに近づけ、安定が続けば四か月に延ばすなど、伸び縮みする設計が現実的です。間隔を延ばして再燃の兆しが出たら、また少し詰める。カレンダーではなく、記録に従って決めるのが、遠回りに見えて最短です。
ホームケアが続かない理由と、現実的に続く方法
“やり方が分からない”より、“続け方が分からない”ことの方が多いと感じます。忙しい日は就寝前の数分が削られ、旅行や繁忙期にリズムが崩れると、そのまま元に戻らない。だからこそ、私は「最小限でもコアになる習慣」を決めることを勧めています。例えば、夜だけは必ず歯間清掃まで行う、週に一度は鏡を見ながらゆっくり磨く、色の濃い飲料の後に水を一口含む。
道具の選択も大切です。フロスと歯間ブラシは“形の合ったもの”にすると負担が激減しますし、ヘッドの小さな歯ブラシは嘔吐反射が強い方でも届きやすい。マウスピース矯正中なら、アタッチメント周囲の清掃手順を組み替える。完璧ではなく、続く設計に置き換えることが、結果として炎症を小さく保ちます。
代官山エリアで通院を続けるための工夫(アクセス・時間設計・組み合わせ受診)
代官山は仕事や子育てで時間が細切れになりやすい街です。通院を継続するためには、生活動線の中にメンテナンスを組み込む意識が役立ちます。例えば、在宅勤務の日の午前中に短時間で、出勤前に一枠だけ、保育園の送迎前後に合わせる、近隣の用事と同日にまとめる。
また、矯正・ホワイトニング・小さな補綴の調整など、互いに影響し合う処置は同日に“束ねる”と来院回数の最適化につながります。メンテナンスの予約枠は“間隔”だけでなく“時間帯”も再発に影響します。疲れている時間を避け、集中できる時間帯に設定する。通いやすさは、継続の最大の味方です。
インプラント・矯正・補綴と「維持期」の接続
インプラントは虫歯にはなりませんが、インプラント周囲炎は起こります。装置周囲の段差や清掃難度、咬合負荷、夜間の食いしばり。これらが揃うと、炎症は静かに進みます。維持期では、インプラント周囲のプロービングと出血のチェック、咬合接触の微調整、必要に応じたナイトガードの再適合を定期的に行います。
矯正治療中は、ブラケットやアタッチメントが清掃のボトルネックになります。力学的に歯周組織へ負担が乗るため、“歯周が整っていること”を前提に力をかけ続ける設計が必須です。補綴では、マージン形態とオーバーコンツアの見直しが炎症の鍵を握ります。維持期での“微調整の積み重ね”が、長期の安定へつながります。
まとめ:小さな変化を見逃さないことが、将来の歯を守る
メンテナンスは、単なるクリーニングではありません。記録と比較に基づく診査、原因へのアプローチ、再発を最小化する設計の総称です。出血点が一つ増えた、ポケットがわずかに深くなった、噛み合わせが少し変わった――その“小さな変化”を、小さいうちに整えること。これが、五年後・十年後の差になります。
生活は完璧でなくて構いません。続けられる方法を一緒に見つけ、現実的なリズムに落とし込み、記録を頼りに微調整し続ける。代官山WADA歯科・矯正歯科は、その伴走を丁寧に行います。
「最近、出血が増えた気がする」「間隔を延ばしてから不安」――そう感じたら、見直しの合図です。どうぞ遠慮なくご相談ください。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
渋谷区代官山T-SITE内の歯を残すことを追求した歯医者・歯科
TEL:050-3188-8587
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2025年 (35)
-
2024年 (34)
-
2023年 (42)
-
2022年 (36)
-
2020年 (1)