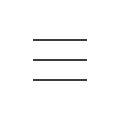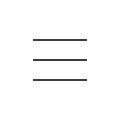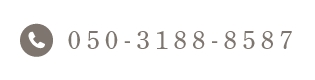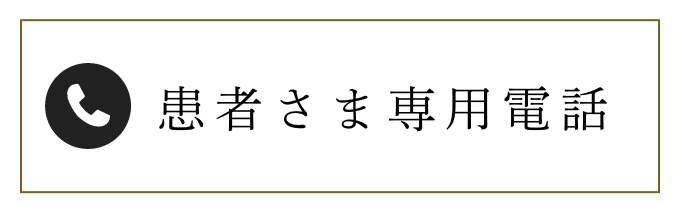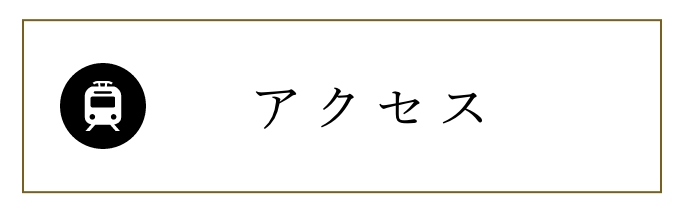ブログblog
歯周病は「命に関わる病気」の引き金?糖尿病・心疾患との意外な関係
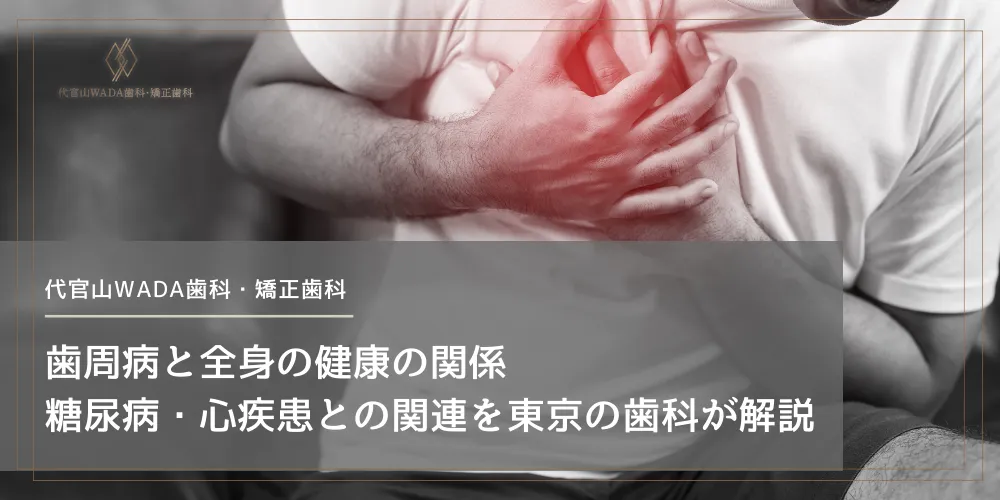
こんにちは。代官山WADA歯科・矯正歯科です。
皆さんは、毎日の歯磨き中に歯ぐきから血が出たとき、どう感じますか? 「あ、また血が出たな。疲れが溜まっているのかな」と、軽く受け流してしまう方がほとんどではないでしょうか。
しかし、もしその出血が、単なるお口の中の傷ではなく、将来的に「糖尿病」や「心筋梗塞」といった命に関わる病気を引き起こすサインだとしたら、どうでしょう。 少し怖く感じるかもしれませんが、これは決して大げさな話ではありません。
近年の医学研究によって、歯周病は単なる「お口の病気」ではなく、全身の健康を脅かす「万病の元」であることが明らかになってきました。 日々の診療でも、お口の状態が改善することで、血糖値が安定したり、体調が良くなったりする患者様を数多く目の当たりにしています。
この記事では、なぜ歯周病が全身の病気とつながっているのか、その意外なメカニズムと、皆さんの健康寿命を延ばすために私たち歯科医ができることについて、専門的な視点からわかりやすくお話しします。
目次
- 1. お口は「全身への入り口」。歯周病が体を蝕むメカニズム
- 2. 糖尿病と歯周病の「腐れ縁」。負のスパイラルを断ち切るには
- 3. 血管を傷つける「静かな炎症」。心筋梗塞・脳梗塞のリスク
- 4. 忙しい現代人ほど危ない。「生活習慣」という共通のリスク
- 5. 内科の薬を飲んでいる方へ。歯科受診時の注意点
- 6. 今日からできる「命を守る」ための生活習慣
- 7. 当院の「医科歯科連携」を意識した診療アプローチ
- 8. まとめ:お口の健康は、全身の健康のバロメーター
1. お口は「全身への入り口」。歯周病が体を蝕むメカニズム
「口は災いの元」と言いますが、医学的にもまさにその通りです。 歯周病は、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)に細菌が溜まり、炎症を起こす病気です。この炎症は、お口の中だけに留まりません。
歯周ポケットから細菌が血管へ侵入する
歯ぐきには無数の毛細血管が通っています。歯周病で炎症を起こした歯ぐきは、いわば「開いた傷口」のようなものです。 ここから歯周病菌や、炎症によって生じた毒性物質(サイトカイン)が血管内に侵入し、血流に乗って全身へと運ばれていきます。 つまり、歯周病を放置することは、常に体中に細菌や毒素をばら撒き続けているのと同じ状態なのです。これが、様々な全身疾患の引き金となります。
2. 糖尿病と歯周病の「腐れ縁」。負のスパイラルを断ち切るには
特に深い関係にあるのが「糖尿病」です。歯周病は、糖尿病の第6の合併症とも言われています。
歯周病を治すと、血糖値が下がる?
糖尿病になると、免疫力が低下するため、歯周病にかかりやすく、また進行しやすくなります。 一方で、歯周病による炎症物質(サイトカイン)は、血液中のインスリン(血糖値を下げるホルモン)の働きを妨げてしまうことが分かっています。 つまり、「糖尿病だから歯周病になる」「歯周病だから糖尿病が悪化する」という、恐ろしい負のスパイラルが存在するのです。
しかし、逆に言えばチャンスでもあります。 歯周病をしっかりと治療し、炎症を抑えることで、インスリンの働きが改善し、血糖値(HbA1c)が下がるという研究結果も多数報告されています。お口のケアは、糖尿病治療の一環でもあるのです。
3. 血管を傷つける「静かな炎症」。心筋梗塞・脳梗塞のリスク
日本人の死因の上位を占める心疾患や脳血管疾患。これらを引き起こす「動脈硬化」にも、歯周病が関与しています。
動脈硬化の原因にもなる歯周病菌
血管に入り込んだ歯周病菌や炎症物質は、血管の内側の壁を傷つけたり、炎症を起こしたりします。すると、血管が狭くなったり、硬くなったりして動脈硬化が進行します。 さらに、動脈硬化を起こした血管のプラーク(コブ)から歯周病菌が見つかることもあり、血栓(血の塊)を作りやすくする原因にもなると考えられています。 心臓や脳の血管を守るためには、血管の入り口であるお口の中を清潔に保つことが非常に重要なのです。
4. 忙しい現代人ほど危ない。「生活習慣」という共通のリスク
歯周病も糖尿病も心疾患も、すべて「生活習慣病」です。これらは別々の病気ではなく、同じ根っこでつながっています。
ストレスや睡眠不足が歯周病を加速させる
忙しい日々の中で、ストレスや睡眠不足を感じていませんか? これらは体の免疫力を低下させ、歯周病菌に対する抵抗力を弱めてしまいます。「忙しい時期に限って歯ぐきが腫れる」のは、体がSOSを出している証拠です。
喫煙は「百害あって一利なし」
タバコに含まれるニコチンなどの有害物質は、血管を収縮させ、歯ぐきの血流を悪くします。酸素や栄養が行き渡らなくなるだけでなく、免疫機能も低下させるため、歯周病のリスクは非喫煙者の数倍に跳ね上がります。また、治療をしても治りにくいという特徴もあります。
5. 内科の薬を飲んでいる方へ。歯科受診時の注意点
全身疾患をお持ちの方の中には、内科でお薬を処方されている方も多いと思います。 歯科治療を安全に行うために、以下の情報は必ずお伝えください。
「お薬手帳」が安全な治療のカギ
- 血液サラサラのお薬(抗凝固薬など): 出血を伴う処置の際に血が止まりにくくなることがあります。
- 糖尿病のお薬: 外科処置後の感染リスクや、低血糖への配慮が必要です。
- 骨粗鬆症のお薬(ビスホスホネート製剤など): 抜歯などの処置後に、顎の骨の治りが悪くなる副作用が出ることがあります。
当院では、患者様のかかりつけ医と連携を取りながら(対診)、お薬を休薬する必要があるか、飲み続けても大丈夫かなどを慎重に判断し、安全第一で治療を進めます。
6. 今日からできる「命を守る」ための生活習慣
将来の大きな病気を防ぐために、今すぐできることは何でしょうか。
「完璧」よりも「継続」が大切です
毎食後の完璧な歯磨きを目指して挫折するより、まずは「夜寝る前だけは丁寧に磨く」ことから始めましょう。デンタルフロスや歯間ブラシを使う習慣をつけるだけで、歯周病のリスクは大幅に下がります。
プロによるクリーニングでリスクをリセット
どんなに頑張って磨いても、自分では取りきれない汚れ(歯石やバイオフィルム)は必ず残ります。 3ヶ月に1回程度、歯科医院でプロフェッショナルケアを受けることで、お口の中の細菌数をリセットし、炎症のない状態を保つことができます。これは、全身の血管や臓器を守るためのメンテナンスでもあります。
7. 当院の「医科歯科連携」を意識した診療アプローチ
代官山WADA歯科・矯正歯科では、単に歯を治すだけでなく、患者様の全身の健康を見据えた診療を行っています。
- 問診の徹底: 全身疾患の有無や服薬状況を詳しくお伺いし、リスクを評価します。
- 歯周病精密検査: 歯周ポケットの深さや出血の有無を数値化し、炎症の程度を客観的に把握します。
- 生活習慣指導: ブラッシング指導だけでなく、食生活や喫煙についてもアドバイスを行い、根本的なリスク低減を目指します。
8. まとめ:お口の健康は、全身の健康のバロメーター
「歯ぐきの出血」は、体があなたに送っている重要なメッセージです。 それを無視して放置するか、それとも健康を見直すきっかけにするかで、10年後、20年後のあなたの健康状態は大きく変わるはずです。
私たちは、歯科医療を通じて、皆様がいつまでも健康で、美味しいものを食べ、笑顔で過ごせる人生をサポートしたいと願っています。 気になる症状がある方はもちろん、「最近、体の健康が気になる」という方も、ぜひ一度ご相談ください。
東京・代官山エリアで、全身の健康まで考えた歯周病治療・予防歯科なら、代官山WADA歯科・矯正歯科にお任せください。 スタッフ一同、皆様のご来院を心よりお待ちしております。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
渋谷区代官山T-SITE内の歯を残すことを追求した歯医者・歯科
TEL:050-3188-8587
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2026年 (2)
-
2025年 (41)
-
2024年 (34)
-
2023年 (42)
-
2022年 (36)
-
2020年 (1)