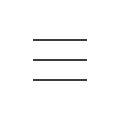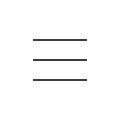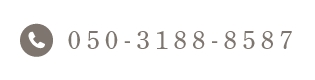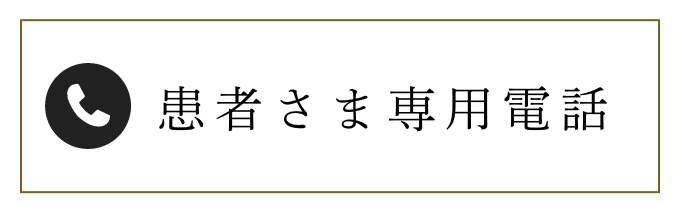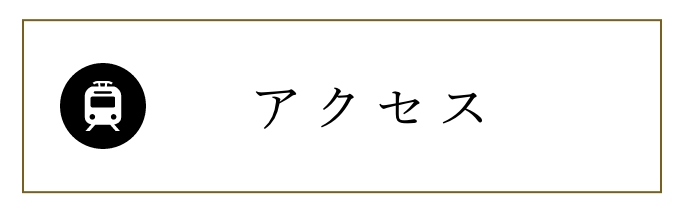ブログblog
インプラント前の歯周病治療が重要な理由|東京の歯科医が徹底解説
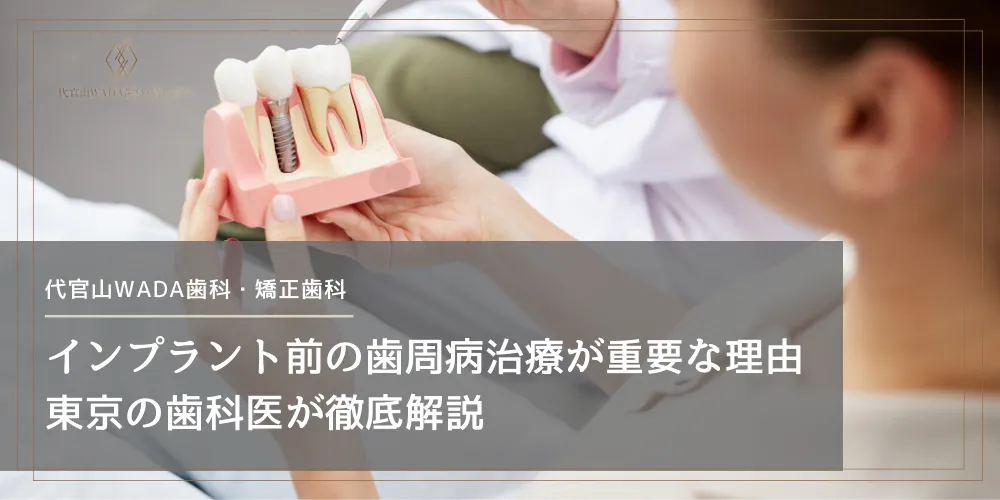
こんにちは。代官山WADA歯科・矯正歯科の歯科医師です。
日々の診療で、インプラントをご希望される方とお話をしていると、必ずお伝えしている大切な前提があります。それは「インプラントは手術の上手さだけで長持ちするわけではない」ということです。土台となる歯ぐきや骨、そしてお口全体の清潔度が整って初めて、インプラントの寿命は大きく伸びます。特に歯周病が背景にある場合、治療を後回しにしたままインプラントへ進むのは、長期的な観点ではおすすめできません。
今日は、なぜインプラント前に歯周病治療が重要なのか、どんな準備が必要なのか、そして手術後にトラブルを避けるための実践的なポイントを、臨床の経験を交えながらお話しします。
1. なぜ「歯周病のコントロール」がインプラントの成否を左右するのか
インプラントは、チタン製の人工歯根を顎の骨に埋め込み、骨と結合(オッセオインテグレーション)させて噛む力を回復する治療です。外科的な手技はもちろん重要ですが、実はそれ以上に結果へ影響を与えるのが「周囲組織の健康状態」です。歯周病は細菌感染による慢性炎症で、歯を支える骨が溶ける病態。歯を失った原因が歯周病であれば、同じ環境(プラークが溜まりやすい、清掃が行き届かない、炎症が常在している)が残っている限り、インプラント周囲でも同様の炎症が再現されやすくなります。
つまり、天然歯で起きていた炎症が、今度はインプラントの周りで起きる可能性が高いということです。ここをきちんと整えないまま手術に向かうと、短期間は問題なくても、数年単位でみると周囲粘膜炎やインプラント周囲炎が起こり、骨が痩せてしまうリスクが高まります。
2. 歯周病とインプラントの関係:見えない炎症が引き起こす三つの問題
第一に、感染の拠点が残っていると、術後の早い段階からインプラント周囲に炎症が波及しやすくなります。炎症は痛みを伴わず静かに進むことが少なくなく、気づいた時には骨の吸収が進行していることもあります。
第二に、歯周病がある口腔内は清掃が難しく、バイオフィルム(細菌の膜)が短期間で再形成されやすい状態です。インプラントの構造上、装置と歯ぐきの境目には汚れが溜まりやすい場所が生まれます。もともとプラークコントロールが苦手な方は、手術後のセルフケア負担がさらに上がるため、炎症を繰り返してしまいます。
第三に、噛み合わせの不均衡や歯ぎしり・食いしばりがあると、インプラント体に過剰な力が集中します。炎症と機械的ストレスが同時に存在すると、骨の吸収は加速しやすくなるため、術前に噛み合わせの評価と調整を行い、リスクを減らしておくことが大切です。
3. 手術前に必ず確認しておきたい評価項目
インプラントの成功は「初期診断の正確さ」に比例します。私たちは、歯周病の治療と並行して、口腔内外の評価を丁寧に行います。全身状態としては、喫煙の有無、糖尿病や高血圧などのコントロール、服用中の薬剤(特に骨代謝に関わる薬)を把握します。局所所見では、歯周ポケットの深さ、出血や排膿の有無、動揺度、プラーク付着の程度、舌や唇の動き、口呼吸の傾向など、清掃性と炎症の指標を総合的に見ます。
さらに、CTで骨の高さ・厚み・形態を三次元的に評価し、神経や上顎洞との距離を確認します。残存歯の予後を見極めることも重要で、保存するのか、抜歯して骨を守るのか、矯正で清掃性を高めるのか、複数の選択肢を並べて、患者さんの生活や価値観に沿って計画を組み立てます。ここを丁寧に行うほど、手術そのものは安全かつシンプルになります。
4. 私たちが行うインプラント前準備の流れ
まずは歯周基本治療から始めます。歯石やプラークを除去し、磨き方を一緒に修正し、必要に応じて噛み合わせの調整を行います。炎症のサイン(出血や腫れ)が鎮静化し、清掃が安定しているかを再評価したうえで、外科のタイミングを判断します。保存が難しい歯は、抜歯と同時に骨の陥凹を予防する処置(いわゆるソケットプリザベーション)を検討します。骨量が不足する部位では、骨造成(GBR)や上顎洞底挙上などの前処置が必要になることもあります。
インプラント埋入は、骨と軟組織の状態、咬合負荷、日常の清掃がコントロールできていることが条件です。術後は安静期間を十分に取り、適切なタイミングで仮歯や最終の被せ物へ移行します。見た目だけを急がず、骨と歯ぐきが安定する順序を守ることが、結果的に美しさと持ちの良さを両立させます。
5. よくある誤解と、トラブルを防ぐための考え方
「歯を抜いてすぐインプラントを入れれば早いし楽」――確かに症例によっては即時埋入が有利に働くことがあります。ただし、炎症が強い部位や骨の欠損が大きい部位では、無理に急ぐより、まず感染を鎮め、骨と歯ぐきの環境を整えたほうが長期成績は安定します。
「歯周病はとりあえず薬で抑えて、手術してから考える」――抗菌薬は補助的に用いることはありますが、薬だけで環境は変わりません。日々の清掃とプロによるメンテナンスが伴わなければ、インプラント周囲でも同じ炎症が再現されます。
「インプラントは虫歯にならないから、ケアはほどほどで良い」――確かにインプラント自体は虫歯にはなりませんが、周囲に付着したバイオフィルムは炎症を引き起こし、骨を失わせます。天然歯以上に、定期的なクリーニングと丁寧なセルフケアが求められます。
これらの誤解は、術後のトラブルに直結します。焦らずに土台を整えることが、遠回りに見えて最短の近道です。
6. 手術直前〜術後早期のケアで差がつくポイント
手術直前は、いつも以上に徹底したプラークコントロールが重要です。ブラッシング圧は強すぎず、装置と歯ぐきの境目に毛先を当てて小刻みに動かす意識を持ちます。歯と歯の間はフロス、隣接面の形が複雑な部位は歯間ブラシを適切なサイズで併用します。うがい薬やジェルは補助的に有効ですが、基本は機械的な清掃です。
術後は、創部を触りすぎない、強いうがいをしない、処方通りに薬剤を使用することが大切です。腫れや内出血は個人差があり、過度に心配する必要はありませんが、痛みや出血が強い、腫脹が増悪していく、違和感が増していくなどの変化があれば、我慢せずすぐにご連絡ください。仮歯の期間は清掃が難しくなるため、通院の間隔を短めにし、プロのクリーニングで負担を分担すると安定が早まります。
7. 代官山WADA歯科・矯正歯科の取り組み
当院では、インプラントを“単独の手術”としてではなく、“お口全体の健康管理の一部”として位置づけています。はじめに歯周基本治療と教育的なクリーニングを徹底し、どの部位が汚れやすいのか、なぜ炎症が繰り返されるのかを、写真や模型を用いて一緒に確認します。CTとマイクロスコープを活用した精密診断、噛み合わせの評価、必要に応じた矯正や補綴との連携まで、長期の安定を見据えた計画を立てます。
また、治療の選択肢は一つではありません。入れ歯やブリッジが適している場合もあります。利点・留意点・費用や通院回数のイメージを丁寧にご説明し、患者さんご自身が納得して選べるようにすることを大切にしています。インプラントを選択された場合も、手術後のメインテナンス間隔やご自宅でのケア方法までを具体的に共有し、先の見通しを持って安心して進められるようにサポートします。
8. まとめ:焦らず整えることが、最短の近道になる
インプラント治療は、失った歯の機能と見た目を回復できる力強い選択肢です。ただし、長く安定させるカギは「手術の前」にあります。歯周病の炎症をきちんと鎮め、清掃の習慣を確立し、骨と歯ぐきの状態を整える――この段取りができていれば、手術はシンプルになり、術後の経過も静かで、長い目で見た満足度が高くなります。
「早く噛めるようになりたい」「見た目を早く整えたい」というお気持ちは十分理解しています。だからこそ私たちは、急がば回れの姿勢で、確かな土台づくりをご提案します。インプラントを検討中の方、歯周病が気になっている方は、まずは現状のチェックから始めてみませんか。
診査・診断から治療計画、術後のメインテナンスまで、一貫して伴走いたします。どうぞ安心してご相談ください。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
渋谷区代官山T-SITE内の歯を残すことを追求した歯医者・歯科
TEL:050-3188-8587
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2026年 (1)
-
2025年 (41)
-
2024年 (34)
-
2023年 (42)
-
2022年 (36)
-
2020年 (1)