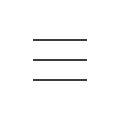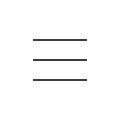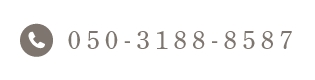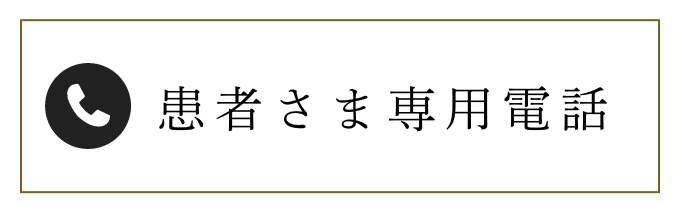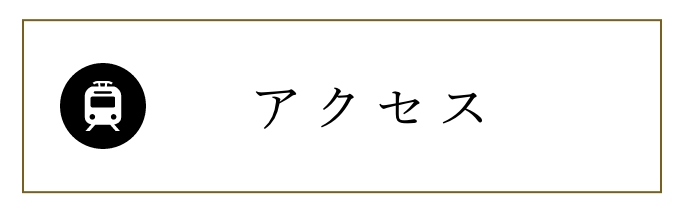ブログblog
「更年期に入ってから、歯ぐきが弱くなった気がする」その理由と対策
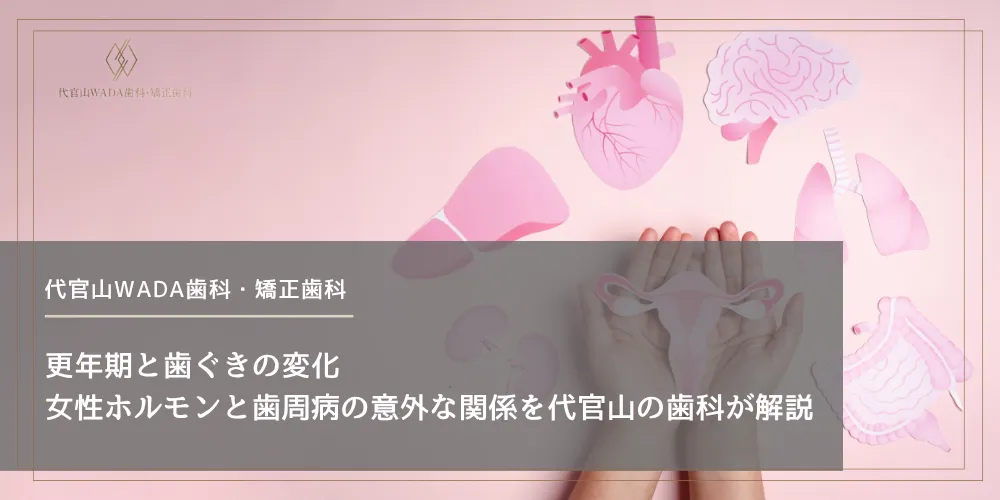
こんにちは。代官山WADA歯科・矯正歯科です。
当院には、40代から50代の女性の患者様が多くいらっしゃいます。 その中で、こんなご相談を受けることが増えてきました。
「昔と同じように磨いているのに、最近すぐ歯ぐきから血が出る」 「口の中がパサパサして、なんとなく口臭も気になる」 「歯医者さんに行かなきゃと思うけど、体調の波があって予約しづらい」
もし、あなたも同じような不調を感じているとしたら、どうかご自身を責めないでください。 「ケアが足りないから」でも「怠けているから」でもありません。 そのお口の変化は、更年期における「女性ホルモンの減少」が引き起こしている、自然な体の反応である可能性が高いのです。
この記事では、更年期を迎えた女性のお口の中で一体何が起きているのか、そのメカニズムと、心身に負担をかけずにできるケアの方法について、院長の視点から優しく解説します。 「ゆらぎ」の時期を、少しでも快適に過ごすためのヒントになれば幸いです。
目次
- 1. その不調、もしかしたら「ホルモンバランス」のせいかもしれません
- 2. エストロゲンが減ると、お口の中はどう変わる?
- 3. 閉経後に注意したい「骨密度」と「歯周病」の関係
- 4. 体調が優れない時の「頑張らない」ケア習慣
- 5. お薬を飲んでいる方へ。歯科受診時のポイント
- 6. 代官山WADA歯科・矯正歯科の「女性に寄り添う」サポート
- 7. まとめ:今の「小さなケア」が、未来の笑顔を守ります
1. その不調、もしかしたら「ホルモンバランス」のせいかもしれません
更年期(閉経を挟んだ前後10年間)は、卵巣の働きが変化し、女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌量が急激に減少する時期です。 エストロゲンは、肌の潤いや髪のツヤを保つだけでなく、実はお口の中の粘膜や骨を守る重要な役割も担っています。
そのため、このホルモンが減ることで、今まで守られていたお口の環境バランスが崩れ、「腫れやすい」「乾きやすい」といったトラブルが起きやすくなるのです。これは誰にでも起こりうることです。
2. エストロゲンが減ると、お口の中はどう変わる?
具体的に、ホルモンの減少がお口にどのような影響を与えるのでしょうか。
① 「バリア機能」が低下して、出血しやすくなる
エストロゲンには、血管をしなやかに保ち、炎症を抑える働きがあります。これが減ると、歯ぐきの血行が悪くなり、少しの刺激(プラークなど)でも過剰に反応して炎症を起こしやすくなります。 「いつも通り磨いているのに血が出る」のは、歯ぐきのバリア機能が弱まり、デリケートになっている証拠です。
② 「唾液」が減って、口臭や虫歯リスクが上がる
「ドライマウス(口腔乾燥症)」も、更年期によく見られる症状です。 エストロゲン低下や自律神経の乱れにより、唾液の分泌量が減ってしまいます。唾液は、お口の汚れを洗い流し、細菌の繁殖を抑える「天然の消毒液」です。これが減ると、お口の中がネバネバしたり、口臭が強くなったり、虫歯ができやすくなったりします。
3. 閉経後に注意したい「骨密度」と「歯周病」の関係
更年期以降、多くの女性が直面するのが「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」のリスクですが、これはお口にも関係しています。
歯を支える骨も、もろくなりやすい時期です
歯を支えている「歯槽骨(しそうこつ)」も骨の一部です。全身の骨密度が低下すると、顎の骨も弱くなりやすくなります。 そこに歯周病の炎症が加わると、若い頃よりも早いスピードで骨が溶け、歯がグラグラになってしまうリスクがあります。 「最近、歯ぐきが痩せてきた気がする」という変化は、骨からのサインかもしれません。
4. 体調が優れない時の「頑張らない」ケア習慣
ホットフラッシュや動悸、イライラなどで体調が優れない時、丁寧な歯磨きをするのは辛いものです。そんな時は、無理をしないでください。
「完璧」は手放して。「夜だけ」丁寧に磨けば合格です
調子が悪い日は、朝や昼はうがいだけでも構いません。その代わり、細菌が増える「寝る前」だけは、座ったままでも、テレビを見ながらでも良いので、時間をかけて磨いてください。 ヘッドの小さな「やわらかめ」の歯ブラシを使えば、デリケートな歯ぐきを傷つけずに優しく磨けます。
パサパサする時は「保湿」を味方につける
お口の乾きが気になる時は、こまめな水分補給に加え、歯科用の「保湿ジェル」や「洗口液(ノンアルコールタイプ)」を活用してみてください。お口の中が潤うだけで、不快感が減り、細菌の繁殖も抑えられます。
5. お薬を飲んでいる方へ。歯科受診時のポイント
更年期障害の治療や、骨粗鬆症の予防でお薬を飲んでいる方もいらっしゃると思います。
ホルモン補充療法や骨粗鬆症のお薬について
- 骨粗鬆症のお薬(ビスホスホネート製剤など): 抜歯などの外科処置をする際に、顎の骨の治りに影響が出ることがあります。
- 向精神薬や睡眠薬: 副作用でお口が乾きやすくなることがあります。
これらのお薬を飲んでいる場合は、必ず問診時にお知らせください。お薬手帳をお持ちいただくとスムーズです。主治医と連携し、安全な治療計画を立てさせていただきます。
6. 代官山WADA歯科・矯正歯科の「女性に寄り添う」サポート
当院では、女性特有の体調の変化に配慮した診療を心がけています。
体調の波に合わせて、無理のない通院プランを
「今日は体調が悪いからキャンセルしたい」 そんな時も、どうぞ遠慮なくご連絡ください。無理をして通院しても、治療がストレスになっては意味がありません。 体調が良い時に集中してケアをする、辛い時は間隔を空けるなど、柔軟に対応いたします。 また、診療中は寒さ対策のブランケットをご用意したり、休憩を挟んだりと、リラックスして過ごしていただけるよう努めています。
7. まとめ:今の「小さなケア」が、未来の笑顔を守ります
更年期は、女性にとって心身ともに変化の大きい「ゆらぎ」の時期です。 お口のトラブルもその一つですが、適切なケアとプロのサポートがあれば、必ず乗り越えられます。
「今は自分の体をいたわる時期」と割り切って、完璧を目指さず、できる範囲でケアを続けていきましょう。 私たちは、そんなあなたを歯科医療の立場から全力でサポートします。 些細なお悩みでも、どうぞお気軽にご相談ください。
東京・代官山エリアで、女性のライフステージに合わせた歯科治療なら、代官山WADA歯科・矯正歯科へ。 スタッフ一同、温かくお迎えいたします。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
渋谷区代官山T-SITE内の歯を残すことを追求した歯医者・歯科
TEL:050-3188-8587
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2026年 (5)
-
2025年 (41)
-
2024年 (34)
-
2023年 (42)
-
2022年 (36)
-
2020年 (1)