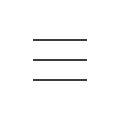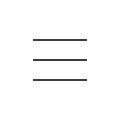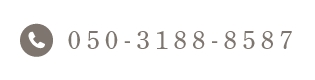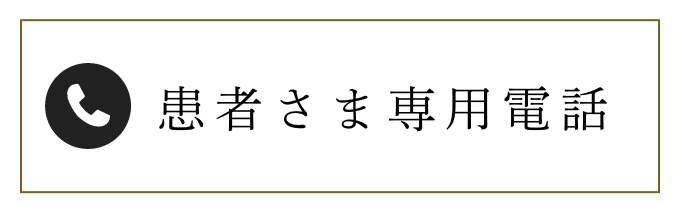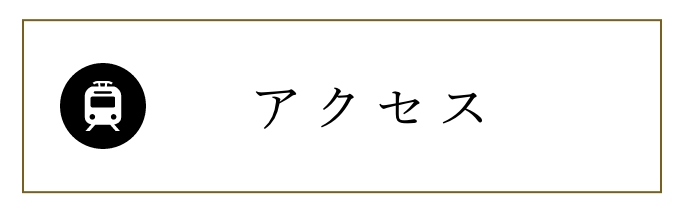ブログblog
歯ぐきが下がる原因とは?代官山の歯科が教える“歯周組織の守り方”
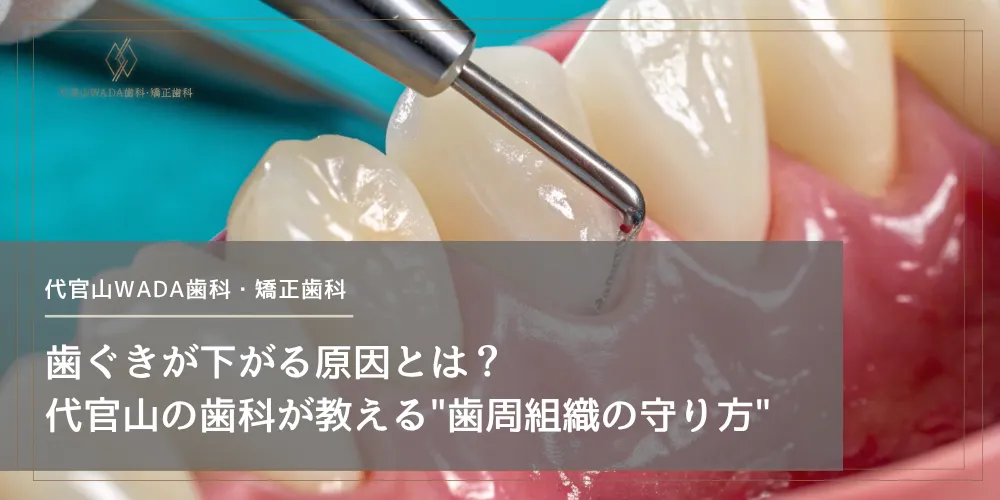
こんにちは。代官山WADA歯科・矯正歯科の歯科医師です。
診療室で「最近、歯が長く見える」「冷たいものがしみる」「前歯のすき間が気になる」とご相談を受けることがあります。いずれも背景にあるのが、歯ぐきの退縮(歯肉退縮)です。歯ぐきが下がると見た目の変化だけでなく、知覚過敏や根面う蝕、歯周病の再発リスク増加など、機能面にも影響が及びます。
本記事では、歯肉退縮が起こる仕組みと主な原因、放置するリスク、そして日常でできる予防・医院で行う治療の選択肢まで、臨床の視点から丁寧に解説します。東京・代官山エリアで忙しく過ごす方でも現実的に続けられる“守り方”を、できるだけ具体的にお伝えします。
目次
- 歯ぐきが下がるとはどういう状態か
- なぜ起きるのか:主な原因と背景要因
- 放置するリスク:見た目・しみる・むし歯化・清掃性の低下
- 自分でできる予防と、今日から変えたい習慣
- 歯科で行う治療の考え方と選択肢
- 矯正・補綴・インプラントと退縮の関係
- 代官山WADA歯科・矯正歯科のアプローチ
- まとめ:小さな変化に早く気づき、静かに守る
歯ぐきが下がるとはどういう状態か
歯肉退縮とは、歯を取り巻く歯ぐき(歯肉)の位置が歯の根の方向へ移動し、根面が露出してくる状態です。原因は一つではなく、炎症による骨の喪失、機械的刺激、薄い歯肉の性質、噛み合わせの負担、口呼吸などが絡み合って起こります。歯肉は“伸び縮みするゴム”ではありません。いったん下がると自然回復は限られ、早期に原因を特定して減らすことが欠かせません。
なぜ起きるのか:主な原因と背景要因
最も多いのは、慢性的な炎症を背景にした歯周病です。歯と歯ぐきの境目に細菌の膜(バイオフィルム)が溜まり、炎症が続くと歯を支える骨がじわじわと吸収されます。骨が痩せれば、その上に乗る歯肉も位置を保てなくなり、結果として下がります。
次に多いのが“力”と“摩耗”の問題です。硬い毛や強すぎるブラッシング圧、横磨きの習慣は、特に犬歯や小臼歯の頬側を傷めやすく、長期的には退縮につながります。歯ぎしり・食いしばりで過剰な力が一点に集中すると、骨や歯肉が薄い部位から退縮が進むことがあります。
生まれつきの“薄い歯肉(シン・バイオタイプ)”も要因です。骨の厚みが薄く、歯根の突出(デヒセンス)があると、わずかな刺激でも退縮しやすくなります。
治療や装置が影響する場面もあります。オーバーコンツア(出っ張った形)の被せ物、深いマージン設定、矯正で歯を歯槽骨の外側へ過度に動かした場合、清掃性の低下や骨の薄さが露呈し、退縮のリスクが上がります。
喫煙、口呼吸、ピアスや楽器による慢性刺激、加齢に伴う歯肉の菲薄化、糖質に偏った間食、睡眠不足やストレスによる免疫低下も、単独あるいは複合して退縮の土壌を作ります。
放置するリスク:見た目・しみる・むし歯化・清掃性の低下
見た目の変化は小さくても、機能的な不利益は大きくなりがちです。根面が露出するとエナメル質に守られていない象牙質が露出し、冷温・甘味・ブラッシングでしみる知覚過敏が起こります。根面はむし歯(根面う蝕)になりやすく、一度できると進行が速いのが特徴です。
歯と歯の間では“ブラックトライアングル”と呼ばれる隙間が目立ち、食片圧入や清掃困難が生じます。清掃性が落ちると炎症が再燃し、さらに退縮が進むという負の循環を招きます。インプラント・ブリッジ・矯正装置が入っている口腔では、清掃の難度がさらに上がるため、早期介入が肝心です。
自分でできる予防と、今日から変えたい習慣
予防の第一歩は、歯ぐきとの境目に“そっと毛先を当てる”磨き方へ切り替えることです。強く擦るのではなく、細かい振動でプラークを崩すイメージに変えると、清掃力は落とさずに歯肉への負担を減らせます。ヘッドの小さな歯ブラシに替える、利き手と逆側を磨く際の姿勢を見直す、といった小さな工夫が継続を助けます。
歯間清掃は、フロスと歯間ブラシを“隙間の形に合わせて”選ぶことが大切です。大きすぎる歯間ブラシは歯肉を傷め、小さすぎると清掃不良になります。サイズの見極めは医院で一度確認しておくと安心です。
夜間の食いしばりが疑われる場合は、就寝前のルーティンを整え、カフェイン・アルコールの時間帯と量を控えることでも負荷が減ります。口呼吸の傾向があるなら、鼻呼吸を意識し、寝具や鼻腔のケアで乾燥を避けると、歯肉の炎症が落ち着きやすくなります。喫煙は退縮と治癒遅延の強いリスクで、減煙でも効果が出ます。
歯科で行う治療の考え方と選択肢
医院での介入は、①原因の除去、②感覚症状への対処、③形態・組織の回復、の順で考えます。
まず、縁上・縁下のプラークコントロールを徹底し、出血点をゼロに近づけます。形態的な問題(オーバーコンツア、深すぎるマージン)は調整・再製作を含めて“汚れがたまらない形”へ戻します。
知覚過敏には、フッ化物・硝酸カリウム等の知覚過敏抑制材、根面の樹脂シーリングなど、非観血的な選択肢で症状を抑えます。根面う蝕があれば、接着を前提に低侵襲で修復します。
歯肉自体の厚みが足りない、審美領域の退縮が目立つ、清掃しても再燃する――こうした場合には、歯周形成外科を検討します。代表的なのは、歯肉を歯冠側へ寄せる“歯冠側移動術(CAF)”と、口蓋から少量の結合組織を採取して厚みを増す“結合組織移植術(CTG)”です。部位や歯肉の厚み、退縮のタイプに応じて、トンネル法や遊離歯肉移植、コラーゲン代替材の活用など、侵襲と回復のバランスを見ながら選択します。術式は“万能”ではありませんが、適切な適応で清掃性の改善・知覚過敏の軽減・審美性の回復が期待できます。
外科の前には、必ず炎症を鎮め、清掃習慣を安定させておくことが成功率を左右します。術後は数週間の安静と指示通りの清掃制限が必要で、無理をしない計画が大切です。
矯正・補綴・インプラントと退縮の関係
矯正治療は、歯を骨の“中心”から外へ押し出す移動が続くと、頬側の骨が薄い部位で退縮リスクが高まります。移動計画の段階でCT評価を行い、力の方向・量・速度を調整することが予防に直結します。治療中はアタッチメントやワイヤーの周囲にプラークが溜まりやすく、炎症管理が後手に回ると退縮が進みやすい点にも注意が必要です。
補綴では、歯頸部の形態が清掃を左右します。段差やオーバーコンツアがあると、どれだけ上手に磨いても汚れが残り、歯肉は退縮方向に逃げがちです。適合の見直しと形態の是正が第一選択になります。
インプラント周囲も同様に“退縮”が問題になります。角化歯肉の幅・厚みが不足し、清掃困難や過剰な咬合負荷があると、インプラント周囲粘膜が下がり、金属の露出やブラッシング痛を招きます。周囲の軟組織移植やアバットメント形態の見直しで、清掃性を高める設計に改めます。
代官山WADA歯科・矯正歯科のアプローチ
当院では、まず“なぜその部位だけが下がったのか”を正面から見極めます。口腔内写真・プロービング・出血点のマッピング、必要に応じてCTで骨の厚みを評価し、原因を炎症・力・形態・生体の薄さ・習癖に分解します。原因が複合していることが多いため、順序立てて一つずつ解決します。
清掃は“根性論”では続きません。生活リズム(出勤・在宅・育児・トレーニング)を伺い、続けられる道具・手順に置き換えます。必要に応じてナイトガードで負荷を分散し、補綴や矯正の形態・力学を微調整します。外科が必要な場合も、適応の可否、得られる改善の幅、ダウンタイム、費用の目安を丁寧に説明し、無理のない計画を共に組み立てます。
代官山という立地特性上、短い枠で少しずつ進める通院の設計も可能です。忙しい時期は清掃指導とメンテナンスを先行し、落ち着いた時期に整形処置へ進むなど、無理をしないが、後回しにしない運び方を大切にしています。
まとめ:小さな変化に早く気づき、静かに守る
歯ぐきの退縮は、痛みもなく静かに進むことが多い一方、一度進むと自然回復は限定的です。早い段階で原因を減らし、清掃しやすい形へ整え、必要があれば組織の厚みを回復する――この順序が、数年後の見た目と機能を決めます。
「最近、歯が長く見える」「冷たい水がしみる」「歯間の影が気になる」。思い当たるサインがあれば、それが見直しの合図です。焦る必要はありません。できることから静かに整えていきましょう。私たちは、そのプロセスに丁寧に伴走します。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
渋谷区代官山T-SITE内の歯を残すことを追求した歯医者・歯科
TEL:050-3188-8587
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2026年 (1)
-
2025年 (41)
-
2024年 (34)
-
2023年 (42)
-
2022年 (36)
-
2020年 (1)