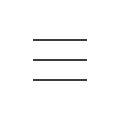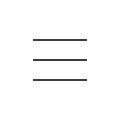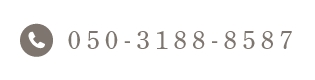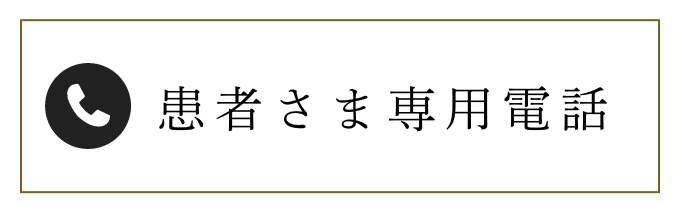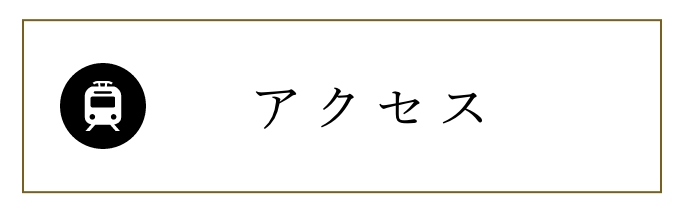ブログblog
歯ぎしり・食いしばりは歯周病を悪化させる?噛み合わせと骨吸収のメカニズム
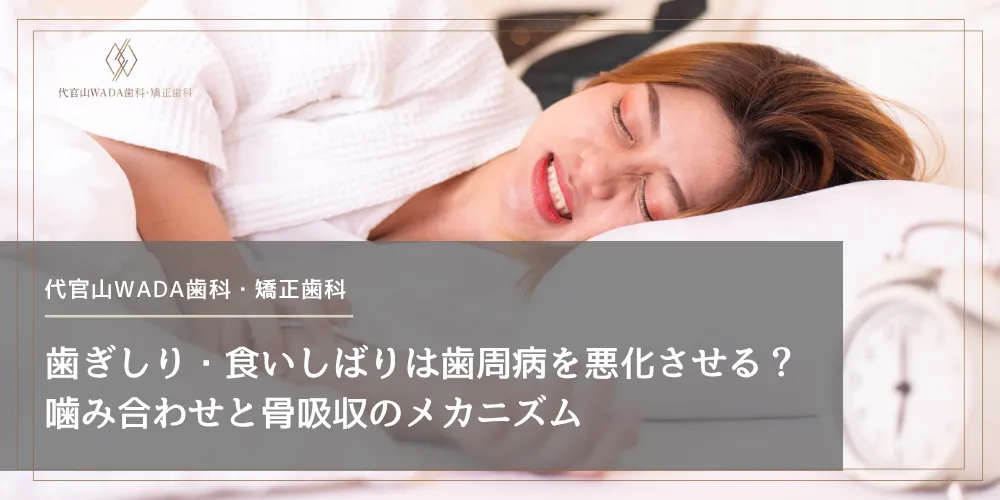
こんにちは。代官山WADA歯科・矯正歯科の歯科医師です。
「歯ぐきの腫れと出血は落ち着いてきたのに、奥歯の周りだけ違和感が残る」「朝起きると歯が浮いた感じがする」——そんな訴えの裏側に、夜間の歯ぎしり(ブラキシズム)や日中の食いしばりが潜んでいることは珍しくありません。歯周病は細菌による慢性炎症が主因ですが、“力”という機械的ストレスが加わると、炎症は深く、骨吸収は速く進みやすくなります。
本記事では、噛み合わせの力が歯周組織に与える影響を、歯根膜・骨のリモデリングという“生体の仕組み”から解説し、診断・治療・予防まで、臨床の現場で有効だった考え方をできるだけ具体的にお伝えします。
目次
- 歯周病は「炎症」だけでは語れない:力学ストレスの影響
- 歯ぎしり・食いしばりが起こすこと:歯根膜と骨のリモデリング
- 一次性外傷性咬合と二次性外傷性咬合の違い
- よくあるサイン:擦り減り・楔状欠損・動揺・フレミタス
- 診断の進め方:問診・触診・咬合接触の評価・画像所見
- 治療の順番:炎症コントロール→力の再配分→維持設計
- 就寝時と日中、それぞれに効く対策
- 矯正・補綴・インプラント症例での“力”の設計
- 再発を防ぐメインテナンス:記録に基づく微調整
- まとめ:炎症を減らし、力を整える——二本柱で守る歯周組織
1. 歯周病は「炎症」だけでは語れない:力学ストレスの影響
歯周病はバイオフィルム(細菌の膜)による慢性炎症が主因ですが、同じ量のプラークでも、過大な咬合力が加わる口では壊れ方が違います。力は歯根膜を介して骨へ伝わり、許容量を超えると線維は損傷し、血流が阻害され、骨のリモデリングが“吸収優位”に傾きます。炎症と機械的ストレスが同時に存在すると、組織は防御ではなく退避を選び、骨縁は下がりやすくなります。
このため、出血や腫れが落ち着いていても、噛み合わせの不均衡が残っているだけで、特定の歯だけが再燃・進行することがあります。治りにくい局所には、力の関与を必ず疑います。
2. 歯ぎしり・食いしばりが起こすこと:歯根膜と骨のリモデリング
歯根膜は、歯をバネのように支える0.2mm前後の軟組織です。過負荷が継続すると、圧迫側で血流が途絶え、ヒアリニゼーション(硝子様変性)が起き、破骨細胞が優位な骨改造が進みます。牽引側では線維の緊張が持続し、骨形成が追いつかないと歯の動揺や歯根膜腔の拡大として現れます。
睡眠中の歯ぎしりは、覚醒時の噛みしめの数倍のピーク荷重がかかることがあり、持続時間は短くても“繰り返し刺激”が累積ダメージになります。日中の食いしばりは、無意識に長時間続きやすく、等尺性収縮による持続圧が歯根膜の微小循環を阻害します。いずれも、歯周組織にとっては“回復時間が足りない”状態を生み、炎症がある部位では吸収が加速します。
3. 一次性外傷性咬合と二次性外傷性咬合の違い
一次性は、健康な支持組織に過大な力が加わって起きるもの(高すぎる詰め物・早期接触・咬合干渉など)。二次性は、支持組織がすでに減っているところに“以前と同じ力”がかかっても起きるものです。
歯周病既往がある方では、同じ噛む力でも二次性になりやすく、水平力や側方力に弱くなります。治療では、炎症を先に鎮めつつ、力の方向・量・接触様式を見直すことが基本になります。
4. よくあるサイン:擦り減り・楔状欠損・動揺・フレミタス
臨床で目にするのは、平滑な咬耗面、頬側の楔状欠損、歯頸部のマイクロクラック、朝の咬合痛、触れると歯が振動するフレミタス、レントゲン上の歯根膜腔拡大、限局的な骨吸収、歯の移動(フレアアウト)などです。これらが出血の少ない部位に併発していたら、力の寄与を疑うべきサインです。
5. 診断の進め方:問診・触診・咬合接触の評価・画像所見
問診では「朝のこわばり」「顎の疲労」「集中時の噛みしめ癖」「睡眠の質・いびき・口呼吸」「カフェイン・アルコールの時間帯」まで伺います。触診では側頭筋・咬筋の圧痛、頬粘膜の圧痕、舌縁の圧痕を確認。咬合紙とシリコン指示材で早期接触・偏った接触・側方干渉を可視化し、必要に応じて咬合診断器で再現します。
画像では、部位特異的な骨吸収、歯根膜腔の不均一な拡大、根尖部の圧痕像、インプラント周囲の糸状骨吸収などを拾います。これらを歯周記録(出血点・ポケット・動揺)と重ね合わせると、炎症と力の交差が見えてきます。
6. 治療の順番:炎症コントロール→力の再配分→維持設計
順序を誤ると長引きます。まずは縁上・縁下のバイオフィルムを断ち、出血をゼロに近づけます。炎症が残ったまま咬合調整をしても、組織の反応が読めません。
次に、早期接触の是正、高すぎる修復物の調整、咬合面の平衡化などで力を“面”に分散させます。必要に応じて暫間被覆冠で高さと形態を仮決めし、症状の推移を見ます。
最後に、保定・ナイトガード・メンテナンス間隔の設定まで含めた維持設計を行い、記録に基づいて微調整を続けます。
7. 就寝時と日中、それぞれに効く対策
就寝時は、カスタムのナイトガードが第一選択です。厚み・硬度・覆う範囲を症例に合わせ、側方運動での干渉を避ける設計にします。鼻閉や口呼吸が強い場合は、耳鼻科的評価や就寝環境の見直しも並走させないと効果が頭打ちになります。
日中は、噛みしめのトリガー認識が鍵です。キーボード・スマホ・運転・重い荷物など、無意識のスイッチを特定し、「上下の歯を離す」「舌先を上顎前方に軽く当てる」などのミニ課題に置き換えます。カフェイン・ニコチン・アルコールは筋の興奮性と睡眠質に影響するため、時間帯をずらすだけでも朝のこわばりが和らぐ方がいます。
ボツリヌス療法は、セルフケアやスプリントで制御困難な症例の補助選択肢として検討します。適応・用量・効果持続・咀嚼機能への影響を説明したうえで、過度な期待は避け、歯周管理と併走させるのが現実的です。
8. 矯正・補綴・インプラント症例での“力”の設計
矯正中は、アタッチメント周囲の清掃難度が上がり、軽度の炎症に“力”が重なると退縮しやすくなります。移動方向・量・速度の調整、力の休止期間、アライナー咬合の管理で防げるケースが多いです。
補綴では、マージン形態とコンタクトの質が清掃性と力の伝達を左右します。高い冠や過度の隆線は、局所の外傷性咬合を招くため、仮歯段階での試行錯誤が重要です。
インプラントは、天然歯の歯根膜という“クッション”がないため、側方力に弱く、過負荷が骨吸収として現れやすい構造です。咬合高径・ガイド・接触点の時間差を調整し、夜間は必ず保護スプリントを併用します。角化歯肉の幅・厚みを確保し、清掃性を優先した上部構造を設計することが、長期安定の土台になります。
9. 再発を防ぐメインテナンス:記録に基づく微調整
メインテナンスは「掃除」だけではありません。毎回、出血点・動揺・プロービング値・フレミタス・咬合接触の写真/動画まで残し、前回と比較します。数値が小さくても変化の“方向”が重要です。
スプリントは消耗品です。摩耗や適合不良が進めば保護力は落ちます。定期的に当たりを調整し、必要なら再製作します。仕事や生活リズムが変われば、食いしばりのタイミングも変わります。生活の変化を治療計画に反映させることが、静かな安定につながります。
10. まとめ:炎症を減らし、力を整える——二本柱で守る歯周組織
歯周病の進行は、細菌による炎症だけで説明できません。炎症(バイオフィルム)を減らすことと同時に、力(咬合ストレス)を整えることが、骨を守る二本柱です。
朝のこわばり、擦り減り、特定の歯の違和感。どれか一つでも心当たりがあれば、炎症と力の両面から状態を“見える化”し、順序立てて整えていきましょう。無理のないやり方であっても、数か月後には歯ぐきの色・出血・動揺・噛み心地に、はっきりと違いが出てきます。私たちは、そのプロセスを丁寧に伴走します。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
渋谷区代官山T-SITE内の歯を残すことを追求した歯医者・歯科
TEL:050-3188-8587
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2026年 (1)
-
2025年 (41)
-
2024年 (34)
-
2023年 (42)
-
2022年 (36)
-
2020年 (1)